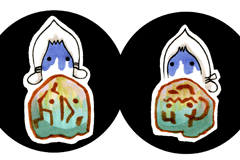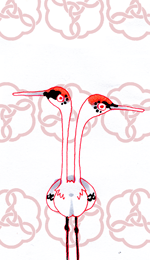氷厘亭氷泉の活動やラクガキをいろいろお届けしているブログです。
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは
きゅうびさんぶんのいち。「さんぼんまっかのきつね」さんです。
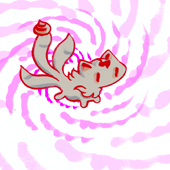
きゅうびさんぶんのいち。「さんぼんまっかのきつね」さんです。
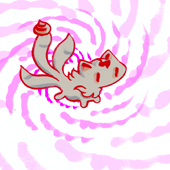
陸奥の国の脇野沢などに伝わる、
おっぽが3本にわかれてるというきつね。
こういうきつねは人間を化かしてくると言われてました。
「まっか」は「また」という意味の方言。
尾のうえに「ほうしのたま」(宝珠)をつけてるとも。
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは
脳痛のモトであります。「のうつうちゅう」さんです。
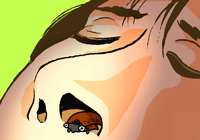
漢字で書くとそのまま。「脳痛虫」ですが
こういう固有名前、というわけではなく、
この虫じたいは、なんていう名前なのか、正確な名前はないのです。
つまり、単なる呼び名なだけです。
人間の体の中に入り込んで、あたまにズンと来る痛みをもたらしてくる虫。
鷹(たか)のくちばしみたいなかたちをしてるといいます。
脳痛のモトであります。「のうつうちゅう」さんです。
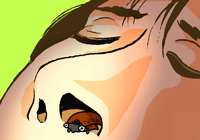
漢字で書くとそのまま。「脳痛虫」ですが
こういう固有名前、というわけではなく、
この虫じたいは、なんていう名前なのか、正確な名前はないのです。
つまり、単なる呼び名なだけです。
人間の体の中に入り込んで、あたまにズンと来る痛みをもたらしてくる虫。
鷹(たか)のくちばしみたいなかたちをしてるといいます。
むかし、あるひとがあたまの痛みに悩んでたところ、
別の人から「そういうときは桃[もも]の葉をまくらにして眠るといい」
と教わったので、さっそく試してみたところ、
眠ってるときに鼻の穴からこれが出て来て、
いままでの痛みがスッキリ治ったんだトカ。
『奇疾便覧』とかにも紹介されてるはなしなので
ほかの説話に輸入援用されてるのかと思いきや
案外、こういう葉っぱまくらで何かを治すはなしというのは
ジャポンにはございませんようで…。
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは
ミリオネアめおと。「がじゃがじゃ」さんです。
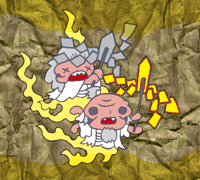
ミリオネアめおと。「がじゃがじゃ」さんです。
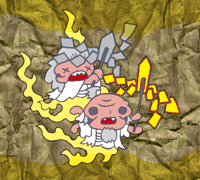
芸州の蒲刈に伝わるもので、真夜中になると
金と銀の御幣(ごへい)を振り回しながら
「がじゃがじゃがじゃがじゃ」と声をたてて
家の中を大きな音を立てながら走り回ったりしたというおばけ。
実は、ものすごい大金持ちだったじいさまとばあさまの霊で、
自分たちが死んだあと、埋めたままになってしまってる大金のありかを知らせたいため、
死後空き家になってしまった自分の家に出てたというもの。
「がじゃがじゃ」(金じゃ金じゃ)とアピールしつつ出てたわけですが
みんなその「がじゃがじゃ」を怖い叫び声だと思ってたという裏目の結果に。
「かねのばけもの」などに近いおはなしです。
プロフィール
■雅号
氷厘亭氷泉(こおりんてい ひょーせん)
■ホームページ
■職業
イラストレーター
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
カテゴリー
最新記事
(01/27)
(01/26)
(01/25)
(01/24)
(01/23)
最新コメント
[01/24 دکوراسیون منزل]
[11/29 NONAME]
[05/08 100]
[01/13 佐藤]
[01/05 ひょ―せん]
アーカイブ
新・妖怪党 部署一覧
Logo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
最新トラックバック
フリーエリア