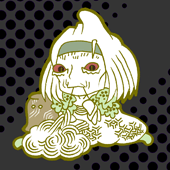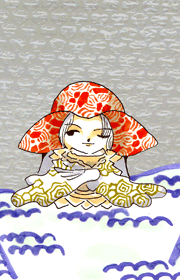しょうたいをあばけ。「しょうぶがさこのばばあ」さんです。

石見の国の国分のあたりにいた「菖蒲がさこ」という呼び名の
長者さんの家の老母を喰べちゃって、その姿に化けてたという大きなねこ。
たくさんのねこをしたがえて人間を襲って食べたりしていましたが、
旅の薬屋に正体をあばかれて退治されてしまいました。
おはなし自体は「かじがばば」(鍛治媼)とか
「やさぶろうばば」(弥三郎婆)とかとおなじ型です。
(途中で呼ばれてくる親分みたいなポジションのやつの名前を
乾分たちが呼んでるのを被害者が覚えてて、その名前とおなじ家をさがしたら
そこの家のひとがひとり喰い殺されてて、実はそれが化けてた、というもの)
オオカミ派とネコ派のさかい目がどのあたりにあるのかは、まだ知らない。
ぶーらぶらっ。「ひょうたんぶらぶら」さんです。

志摩の国の和具などにつたわるもので、
いうことをきかない子供がいると、
夜にひょうたんがぶらぶらと飛んで来る、といったもの。
いうことをきかない子供にものごとを言い聞かせるために
つかわれる、しつけのためのものなので
実際、そういうのがいる、というものではないのですが
「おばけこわい、ひーこわい」
「妖怪なんてのはひょうたんがぶらさがってるようなものよ」
っていう内容の昔話もあるのとあわせて見ると
「なんだ、そんなものか」と、ホッとするがわのひょうたんが
ぶらぶらしてるのがコワイ、というこの背反する立場がそれぞれあるのが
ちょっとおもしろい感じ。
ああ、ひょうたんはナゾの植物にてありぞ。
影をのむ。「おはんさん」さんです。

相模の国の戸塚にあった「影取池」(かげとりいむ)にすんでいた巨大な大蛇。
池のちかくを通るひとの影を取って、そのひとがボーッとしてしまったところを狙って
持っているたべものを盗って食べてたといいます。
(影をとられると、実際、どういうことになるのかは、実はあんまりよくワカンナイ
でも、何かあるようで、みんな持ってた荷物のお米などを盗られてしまったそうです)
もともと、藤沢の遊行寺の近くにすんでいた
「森」という名前の長者の家で飼われていた大蛇だったのですが、
大きくなって蔵のたべものを勝手に食い尽くしてしまうことから、この池に放され、
その後に通行人をおそうようになったんだトカ。
「おはん」というのは、長者の家で飼われていたときの名前。
この呼び方をされて安心をして水から顔をだしたところを鉄砲で撃たれ、死んでしまいました。
げだつせよ。「おみやのばけもの」さんです。

相模の国の石川にあった諏訪神社のお宮に出たという
なぞのばけもの。
ものすごく大きくて、人間をつかまえては食べたりしていたんだとか。
しかし、日頃から「じょうぶつしたい」と本心では思っていたそうで、
あるとき、お宮の近くで赤ちゃんのおもりをしてたひとが、
どんな子守歌をうたっても泣き止まない赤ちゃんに対して、
最後の手段としてうたってたお経の文句をききつけ、
それを一心に願い込んで、ついに成仏することが出来たといいます。
妖怪が、自分の境遇から成仏することで逃れるという発想は、
「うえたばけもの」の話のように、この話が天竺や漢土のものを受けて
構成されていることを示していると考えられます。
ありふみさんの解説の白眉。「うみぺろりん」さんです。

海の岩穴などにすんでるという良いおばけ。
海蛇や「うみぼうず」(海坊主)、「ふなゆうれい」(船幽霊)などが近づいていると、
舟の上のにんげんにぴきょぴきょ音を出して知らせてくれるんだトカ。
……なんてきゅあんな設定!!
佐藤有文せんせいは図鑑のなかで
「いまでは海蛇のエジキとなって全めつした」
と書いていたりもして、
……レッドリストどころではなく、すでに絶滅種!!
なかなかすごいことになってるのですが、この妖怪は
「海ぴろりん」というものが実際のモトのようです。
(ただし、ぴろもぺろもどっちも伝承を完全にベースにしてるものでは無いみたい)
かねをたべます。「かねをくうむし」さんです。

かねはかねでも、ならすかね。梵鐘をたべちゃう虫です。
伊賀の国の阿保村にでた、というはなしのあったふしぎな虫で、
何匹も何匹もあらわれて梵鐘を食べて食べて食べて
ボロボロ穴をあけてしまったんだトカ。
むかし、
ある男と恋仲になった娘さんがいたのだけど、
その娘の親がそれを大いにいましめて反発。
娘が恋人からもらった「鏡」を取り上げて、この梵鐘の材料として寄進してしまったのが、
そもそもの話なんだそうで、その娘のうらみが虫になって
梵鐘をモジョモジョ喰べたんだトサ。
かねにうらみはかずかずござるの、ヘビじゃない版ですね。
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
Logo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党