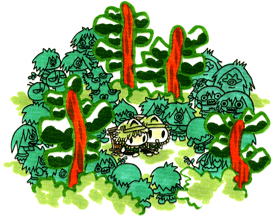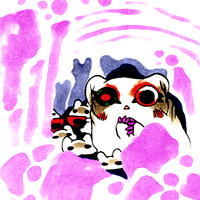ザック。ザック。「あずきとぎのばばあ」さんです。

常陸の国、里美村の捩首(ねじくび)という場所に出ると言われてたもの。
「あずきあらい」の仲間で、この場所で耳を澄ましてると
「あずきとぎましょ人取って喰いましょかざっくざっくざっくざっく」
とうたっているのが聴こえたと言います。
また、夕方おそくまで遊んでる子供に、
これが来るぞと言っておどかしたりもしていたそうです。
一部分は「モウコ系統ガゴ系統」な感じなのですね。
「あずきあらい」
「あずきとぎ」
「あずきすり」
「あずきそぎばば」
「あずきとぎのばばあ」
「あずきばばあ」
「あずきあらいだぬき」
「せんたくばば」
「はしあらい」
と、かなりならんで来ました。さらさらさら。
なお、今年も半分こをすぎましたので
缶にアップした連中の新鮮さがもれださないように
押戻のキャラクターを投入です。「たけくりひなえもん」さんです。

ひよこみたいなのを履いてるんだよ。ぴわぴよ。
ぴかぴかぴかぴかぴかぴか。「こがねのはしら」さんです。
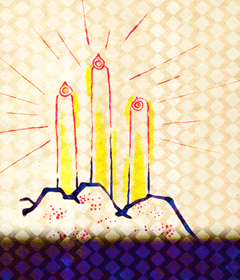
むかし、越前の国は坂井郡の稲越の神明社に
ズドーンと立っていたという3本の黄金の柱。
ぴかぴかきらきら光りを放ち過ぎて、夜でもその光は遠くから見えた
というほどのおそろしいものだったので、
このぴかぴかのすごさのせいで漁をすることが出来ず
困ってしまったひとびとが
「これを焼こう」
と相談。えらばれた7人の蜑女(あま)たちが
なんとかそれを決行して燃やしてしまうのですが、
近くで休んでいたところ急に休んでいた土ぐろが7つに砕けて
蜑女をおしつぶしてしまったんだソウナ。
この蜑女たちがおしつぶされてしまったあたりについた地名が
坂井郡伊井村の「七つぐろ」という地名なんだそうです。
それにしても、この黄金柱、なんで立ってたのかね。
耳の工事。「やまのあやしきひと」さんです。

むかし、但馬の国のあるお寺にいた道幸(どうこう)という僧侶が、
「魔物がでる」とか「ばかでっかい山伏が出る」とか「高入道がでる」とか噂されてた
寺の裏山に、本当にそんなもんがあるのかどうなのか確かめにゆくことに。
入ってみても何も起きなかったので「気の迷いだったんじゃろう、へへーん」と、
山に行った証しに木の皮を削って下山しようとすると、
ふしぎと辺りが真っ暗になって嵐が起こり
「こたびは許すとも、ついには命はあるまじ」
と不気味な声が。
すると、その四五日後、夢のなかに1寸ぐらいの大きさの立派な衣冠をつけたひとと
その供ぞろいたちが現れて、
「今日よりそのほうの命を毎日毎日ちぢむるなり」
と告げると、しもべに鋤鍬(すきくわ)を使って道幸の耳の中から
あぶらみたいなふわふわしたものを掘り出させます。
道幸は「……これは何だろう」と思っていましたが、
その後、毎夜毎夜ふわふわを掘り出されるたびに道幸は痩せてゆき、
2ヶ月後に死んでしまったんだトカ。
こいつは『新説百物語』にあるはなしで、元文のころ(1736-1740)の事としてあります。
『稲生物怪録』や、もっとむかしの百物語の本などにもある
魔所などおそれるに足りぬと言って乗り込んだひとが襲われる話のひとつで、
1寸くらいのちまちましたひとが、耳から何かを掘り出すのは面白い型。
小さい頃から、すきなおはなしの一ッです。
スネークヘッドの呪い。「へびだ」さんです。

むかし、ある男が借金のかたに取った田んぼで草取りをしてると、
うっかり鎌でへびの首を切ってしまいます。あたりを探しても頭がみつからなかったが、
家に帰って水をのもうと水甕(みずがめ)をのぞきと、そこにへびの頭が。
男はおどろいて、それを潰して殺してしまいますが、
その後もたびたび怪しいへびが田んぼに出て、ついに男は
その田んぼを手放してしまったんだトカ。
「あくだ」(悪田)や「えんぎだ」(縁起田)、「やみだ」(病田)など、
けちがついた田畑にまつわるものの仲間な、信濃の国におはなしです。
へびは、田んぼを取られてしまった家の者の恨みが化したものだと言われたソウナ。
どんどんほいほい、「しらとりやまのしろぼうず」さんです。
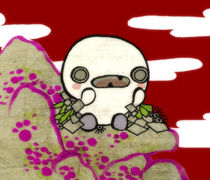
駿河の国の富士郡、白鳥山にいたというもの。
むかし、長貫という地域でどんどん焼きをしていたところ、
決まってこの白鳥山から白坊主が「ほーいほーい」と声をあげて呼ばってくるので、
ひとびとは気味悪がってどんどん焼きをしなくなってしまったと言われていました。
「なんであの地域はアレをやらないの?」といった
行事にかんする言い伝えに出て来るものですが
どんどん焼きに反応してた以外に、どんなことをやってたのかは
あんまりよくワカンナイ。
しろしろぼうず、しろぼうず。
おはぐろフィーバー!! 「つだがえ」さんです。

「つだがえ」ってというのは、「付いたかな?」とか「付いたかえ?」という意味。
陸奥の国の五戸につたわるもので、きつねの化け種目の一ッ。
道に迷ってしまった男が(この男というのは、これ以前の道の途中で眠ってた狐を
「ワー」と大きな声でびっくりさせていて、狐がその仕返しをするというのが話の骨)
ある一件の家に泊めてもらうのですが、そこの家には死人があって、
それが家の中に寝かせてあるという、なかなか怖い状況。
すると家のひとが「ちょっと親戚のところに行くので留守番をしてくれ」と外出。
死人とふたりっきりで暗い中まっていると、
死人が立ち上がっておはぐろをつけだし、
「付だがえ、付だがえ」
と聞き続けてきたので、怖くて怖くて
「付だぁ」
と言ってやると、死人がおどりかかって来たので大慌て、
あっちこっちに逃げまわっていると、
「おい、そこのひと、いばらやぶの中で何をドサクサ騒いでるんだ」
と通行人に声をかけられ、我にかえったんだトカ。
おはなしとしては、きつねやたぬきが人間におどかされた仕返しをする
典型のながれなのですが、おはぐろでギャーというものは、
「ついたかみてくろ」や「おはぐろべったり」の仲間にあたるおどかし術。
こつこつしょぼふる雨のおつかい、「ばけこぞう」さんです。

大きな笠をかぶって、豆腐のおつかいをしてる姿をしてるおばけ。
「とうふこぞう」(豆腐小僧)とは大体おなじものです。
目の玉がひとつだったりして、その顔でひとをびっくりさせるみたいです。
名前のごとく、おつかいの小僧さんの姿のおばけですが
絵によっては、尻尾やおキンなどが描かれてたりして、
こちらも豆腐小僧な妖怪同様、正体はたぬきだったりかっぱだったりするみたいです。
錦耕堂の『をりかはりゑ』(折り変わり絵)という
きってたたんで絵がかわるおもちゃ絵では
おりたたむとカカシになる絵で描かれてたりします。
やっぱり、おっきな笠がポイントなんでござんすナー。
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
Logo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党