氷厘亭氷泉の活動やラクガキをいろいろお届けしているブログです。
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは、
とりしまるがわ。「じゅうごしゃぐう」さんです。
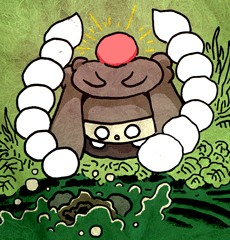
「十五社宮」というのは、阿蘇に祀られてる阿蘇十二社に、
とりしまるがわ。「じゅうごしゃぐう」さんです。
肥後の国の天草で大小色々な規模で祀られてたかみさま。
「がわんた」などのかっぱたちに取り憑かれたときは、
十五社に行って拝むと、とても効果があると
むかしはよく語られてたそうです。
十五社に行って拝むと、とても効果があると
むかしはよく語られてたそうです。
「十五社宮」というのは、阿蘇に祀られてる阿蘇十二社に、
天照大御神・八幡大菩薩・春日大権現
(あるいは、天照大御神・天児屋根・八幡大菩薩など)の三社を足した
15の神々を祀ったもの。
(あるいは、天照大御神・天児屋根・八幡大菩薩など)の三社を足した
15の神々を祀ったもの。
キリシタンのいた地域(一時、寺社が無くなってた地域)に
あとから代官の指導でこれが設置されたそうで、
天草の各地に十五社宮は数多くあったんだソウナ。
あとから代官の指導でこれが設置されたそうで、
天草の各地に十五社宮は数多くあったんだソウナ。
プロフィール
■雅号
氷厘亭氷泉(こおりんてい ひょーせん)
■ホームページ
■職業
イラストレーター
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
カテゴリー
最新記事
(01/13)
(01/12)
(01/11)
(01/10)
(01/09)
最新コメント
[01/24 دکوراسیون منزل]
[11/29 NONAME]
[05/08 100]
[01/13 佐藤]
[01/05 ひょ―せん]
アーカイブ
新・妖怪党 部署一覧
Logo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
最新トラックバック
フリーエリア
