氷厘亭氷泉の活動やラクガキをいろいろお届けしているブログです。
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは、
夫と慕霊とずんだ餅。「いく」さんです。

夫と慕霊とずんだ餅。「いく」さんです。
新助という男と仲睦まじく暮らしてた妻で、
若くして胸の病で亡くなる際に言い残した
「決して後妻はとらないで下さい」とう念が、
この世に残ったと言います。
若くして胸の病で亡くなる際に言い残した
「決して後妻はとらないで下さい」とう念が、
この世に残ったと言います。
1年後に後妻をとった新助が仏壇を拝むと、
銭が1枚飛び出して来て、ひたいにぴったり貼りついて、
どうしても取れなくなってしまいました。
銭が1枚飛び出して来て、ひたいにぴったり貼りついて、
どうしても取れなくなってしまいました。
後妻にも何か起こらないかと気になった新助が、
何とか妻の霊のこころを落ち着けようと、
ずんだ餅(いくの大好物)をつくってあげたところ、
銭はひたいから落ちたソウナ。
何とか妻の霊のこころを落ち着けようと、
ずんだ餅(いくの大好物)をつくってあげたところ、
銭はひたいから落ちたソウナ。
山田野理夫『東北怪談の旅』の「ズンタ餅」(ズンダ餅)に出て来るもの。
福島県相馬の新地村のはなしだと舞台設定されてます。
福島県相馬の新地村のはなしだと舞台設定されてます。
飛んで来て新助に貼りついた銭は、六文銭の1枚だと描写されており、
いくがあの世に行くために持たされてた1枚を投げたものだとわかります。
いくがあの世に行くために持たされてた1枚を投げたものだとわかります。
PR
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは、
目でみつけます。「さごいち」さんです。

漢字で書くと三五市で、死後、手のひらに目玉のついてる
「てのめ」(手の目)のすがたになってしまった目の見えない男。
目でみつけます。「さごいち」さんです。
漢字で書くと三五市で、死後、手のひらに目玉のついてる
「てのめ」(手の目)のすがたになってしまった目の見えない男。
とある場所の野原で三五市は殺されたのですが、
その後、手のひらに出来た目玉でさぐりさぐり歩き回り、
遂には逃げ去ってた相手を見つけ出して、
うらみを晴らしたんだソウナ。
その後、手のひらに出来た目玉でさぐりさぐり歩き回り、
遂には逃げ去ってた相手を見つけ出して、
うらみを晴らしたんだソウナ。
山田野理夫『おばけ文庫 べとべとさん』の「手の目」で書かれてる
手の目妖怪のはなしのひとつ。
手の目妖怪のはなしのひとつ。
石燕の絵などを通じて紹介された「手の目」をしたじきに描かれたもの。
「市」の字があるので意図としては座頭さんとも考えられるのですが、
挿絵では髷のついたすがたで描かれてるので、
座頭さんなのか目の悪いひとだったのかの判断はつきづらくなってます。
「市」の字があるので意図としては座頭さんとも考えられるのですが、
挿絵では髷のついたすがたで描かれてるので、
座頭さんなのか目の悪いひとだったのかの判断はつきづらくなってます。
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは 、
からんからんからん中身はあるよ。「やかんざか」さんです。
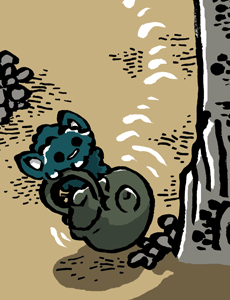
からんからんと音をたてながら
薬缶(やかん)が転がって来るというふしぎな坂道のこと。
からんからんからん中身はあるよ。「やかんざか」さんです。
からんからんと音をたてながら
薬缶(やかん)が転がって来るというふしぎな坂道のこと。
中身が空っぽのような音をたてて
転がって来る薬缶ですが、中身として
とても良いお酒が入ってたりもするソウナ。
転がって来る薬缶ですが、中身として
とても良いお酒が入ってたりもするソウナ。
山田野理夫『おばけ文庫 べとべとさん』の「やかんざか」にあるもので、
仙台の中目慶之進(なかめけいのしん)という武士が
これを持って帰って中身を飲んだが、いつの間にか消えてしまい、
以後は坂道でも出遭うことが出来なかったというはなしになってます。
仙台の中目慶之進(なかめけいのしん)という武士が
これを持って帰って中身を飲んだが、いつの間にか消えてしまい、
以後は坂道でも出遭うことが出来なかったというはなしになってます。
「やかんつる」(薬缶吊)と同じように、薬缶な妖怪の
中身を飲んだという展開は野理夫作品に共通して出て来るパターン。
中身を飲んだという展開は野理夫作品に共通して出て来るパターン。
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは、
お姫さまを奪ってしまいました。「なるとのりゅうじん」さんです。
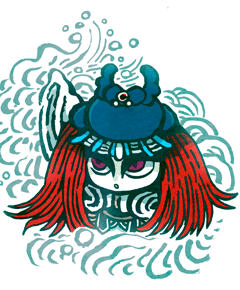
7月は、山田野理夫のお誕生日が来る月だといいうことで
2022年(100周年)2023年(101周年)に引き続いて
今年も102周年記念として、山田野理夫が作品や解説に出してるかたがたを
アップしてゆく特集にておとどけいたします。
「山田の歴史を語る会」のページにも
102周年のバナーなどを設置しました。
そんな2024年のNORIO特集の、いちばんはじめにアップするのは
お姫さまを奪ってしまいました。「なるとのりゅうじん」さんです。
7月は、山田野理夫のお誕生日が来る月だといいうことで
2022年(100周年)2023年(101周年)に引き続いて
今年も102周年記念として、山田野理夫が作品や解説に出してるかたがたを
アップしてゆく特集にておとどけいたします。
「山田の歴史を語る会」のページにも
102周年のバナーなどを設置しました。
そんな2024年のNORIO特集の、いちばんはじめにアップするのは
阿波の国の鳴門の海にいる海の神。
むかし、土佐の国に流されてしまった尊良(たかなが)親王のあとを追い、
舟に乗って出発したお姫さまがいたのですが、
その美しさに惹かれたこの竜神は、大きな渦を起こして舟を巻き込み、
お姫さまを奪ってしまいましたソウナ。
舟に乗って出発したお姫さまがいたのですが、
その美しさに惹かれたこの竜神は、大きな渦を起こして舟を巻き込み、
お姫さまを奪ってしまいましたソウナ。
山田野理夫『海と湖の民話』の「小袖貝」のはなしに書かれてる存在。
『太平記』(巻18)にある尊良親王・秦武文・松浦五郎らの登場するはなしを
下敷きにしたもの。お姫さまは『太平記』でいうところの御息所さま。
各地域の伝説としても、実際このように簡略化されたり、
語り替えられたりした設定のものは語られる上で存在してたと見られます。
下敷きにしたもの。お姫さまは『太平記』でいうところの御息所さま。
各地域の伝説としても、実際このように簡略化されたり、
語り替えられたりした設定のものは語られる上で存在してたと見られます。
プロフィール
■雅号
氷厘亭氷泉(こおりんてい ひょーせん)
■ホームページ
■職業
イラストレーター
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
カテゴリー
最新記事
(01/13)
(01/12)
(01/11)
(01/10)
(01/09)
最新コメント
[01/24 دکوراسیون منزل]
[11/29 NONAME]
[05/08 100]
[01/13 佐藤]
[01/05 ひょ―せん]
アーカイブ
新・妖怪党 部署一覧
Logo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
最新トラックバック
フリーエリア
