氷厘亭氷泉の活動やラクガキをいろいろお届けしているブログです。
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは
もぐらもぐらもぐら。「こうぼうさまのもぐら」さんです。

もぐらもぐらもぐら。「こうぼうさまのもぐら」さんです。
むかし、もぐらはいなかったそうで
弘法大師が人々が畑をたがやすのに便利になるであろう
と考えてもたらしたのですが、どんどん数が増えに増えてしまい
逆に畑を荒らしたりするようになってしまったソウナ。
弘法大師が人々が畑をたがやすのに便利になるであろう
と考えてもたらしたのですが、どんどん数が増えに増えてしまい
逆に畑を荒らしたりするようになってしまったソウナ。
もぐらというものはそれ以来、
とってもとってもとってもいなくならないトカ。
とってもとってもとってもいなくならないトカ。
周防の国の玖珂郡などにつたわる昔話にあるもので、
唐からあるいは四国から弘法大師が持って来たが
「弘法の誤り」であったというもぐらのはじまり。
唐からあるいは四国から弘法大師が持って来たが
「弘法の誤り」であったというもぐらのはじまり。
PR
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは
風とおしのいいお寺にあつまろう。「けだもののばけもの」さんです。
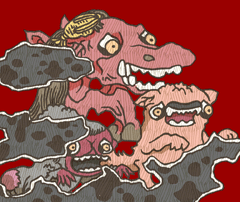
犬や馬や猿などいろんなけもののばけものたちが
古い荒れ寺などにいるというもの。
風とおしのいいお寺にあつまろう。「けだもののばけもの」さんです。
犬や馬や猿などいろんなけもののばけものたちが
古い荒れ寺などにいるというもの。
むかし、ある旅の六部さんが宿にするために荒れ寺に入るのですが、
夜になるとこのばけものたちがぞろぞろと出没。
おどろいて逃げ出したのですが、馬が投げつけてきた馬のわらじが足に激突。
なんとか逃げのびた六部がその足をはっきり見てみると、
もしゃもしゃと馬の毛が生えていて、馬のようになってしまってたソウナ。
夜になるとこのばけものたちがぞろぞろと出没。
おどろいて逃げ出したのですが、馬が投げつけてきた馬のわらじが足に激突。
なんとか逃げのびた六部がその足をはっきり見てみると、
もしゃもしゃと馬の毛が生えていて、馬のようになってしまってたソウナ。
羽後の国の角館などにつたわる昔話に出て来るもので、
逃げるさいに当てられたものによって当てられた箇所が獣になってしまうという展開は
猫の住んでいる土地に行ってしまう昔話(ねこ岳のはなしなど)にも見られるもの。
逃げるさいに当てられたものによって当てられた箇所が獣になってしまうという展開は
猫の住んでいる土地に行ってしまう昔話(ねこ岳のはなしなど)にも見られるもの。
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは
植物性推奨。「いしゃのゆうれい」さんです。

植物性推奨。「いしゃのゆうれい」さんです。
むかし、禽・獣・鱗・介・虫とあらゆる生き物の薬効を試験して
その知識を書物にして世にひろめようとしていたとても賢い医者がいましたが、
あるとき、その弟子の医者のひとりが頓死。
しばらくするとその弟子の医者の幽霊が出現して
「吾が師、幽界では活物たちが師の書ひとたび世に出れば、
皆がその薬効目当てに有情の物の多くが捕り殺され尽すであろうと
禽獣などが言っており、もしかかることがあれば師にわざわいをなさんとも語っております、
諸人に殺生をさせぬため、書を出すのは止めたまえ」と告げて消えます。
その知識を書物にして世にひろめようとしていたとても賢い医者がいましたが、
あるとき、その弟子の医者のひとりが頓死。
しばらくするとその弟子の医者の幽霊が出現して
「吾が師、幽界では活物たちが師の書ひとたび世に出れば、
皆がその薬効目当てに有情の物の多くが捕り殺され尽すであろうと
禽獣などが言っており、もしかかることがあれば師にわざわいをなさんとも語っております、
諸人に殺生をさせぬため、書を出すのは止めたまえ」と告げて消えます。
それを聴いた賢い医者は、
生き物の薬効をおもに記していたいままでの草稿を焼き捨てて、
草木の薬効をおもに記した書を改めて世に出したソウナ。
生き物の薬効をおもに記していたいままでの草稿を焼き捨てて、
草木の薬効をおもに記した書を改めて世に出したソウナ。
『奇談雑史』などに見られる説話にみえるもの。
「幽界」という呼び方は原書にあるもの。
「幽界」という呼び方は原書にあるもの。
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは
本場?の竜宮器具。「とうじんへい」さんです。

本場?の竜宮器具。「とうじんへい」さんです。
竜宮の竜王がもっているというたからもののひとつ。
望みのものを言うと、たちどころに出してくれる瓶。
望みのものを言うと、たちどころに出してくれる瓶。
むかし、兄弟がいたのですが
親が亡くなった時に小さい一番下の弟をがらくたとともに追い出してしまいます。
弟がもう死んでしまおうと悲しんで海辺で唄っていると、
その声が竜宮の竜王の耳に聴こえ、竜王は夜叉たちに
「この唄声のぬしをさっそく呼んで来い、ぜひじっくり聴きたい」と命令。
親が亡くなった時に小さい一番下の弟をがらくたとともに追い出してしまいます。
弟がもう死んでしまおうと悲しんで海辺で唄っていると、
その声が竜宮の竜王の耳に聴こえ、竜王は夜叉たちに
「この唄声のぬしをさっそく呼んで来い、ぜひじっくり聴きたい」と命令。
弟は海辺まで出て来た夜叉につれられて竜宮にいきますが、
そのとき夜叉から
「我が君さまから、何か欲しい物があるかと言われたら、
豆人瓶をください他のものはたとえ宝物であろうが何一つ欲しくはございません
と言いなさいナ、きっと助かりますよ」と助言されたので、唄を披露 したあとに、
早速そのように言上、この瓶を持ち帰りました。
そのとき夜叉から
「我が君さまから、何か欲しい物があるかと言われたら、
豆人瓶をください他のものはたとえ宝物であろうが何一つ欲しくはございません
と言いなさいナ、きっと助かりますよ」と助言されたので、唄を披露 したあとに、
早速そのように言上、この瓶を持ち帰りました。
帰って来たものの、家もない弟が「ああとんでもなく大きい屋敷があればなあ」とつぶやくと、
たちどころに広大な屋敷がズドン! 中に入るといろんな家具やら品物やらももりだくさん。
やがて、弟のうわさをききつけた兄や兄嫁たちがこのひみつを知って
瓶を借りていってしまいますが、欲張ってしまったために家は壊れて
この瓶も壊してしまったソウナ。
たちどころに広大な屋敷がズドン! 中に入るといろんな家具やら品物やらももりだくさん。
やがて、弟のうわさをききつけた兄や兄嫁たちがこのひみつを知って
瓶を借りていってしまいますが、欲張ってしまったために家は壊れて
この瓶も壊してしまったソウナ。
山西省などにつたわる昔話にあるもの。
かわいそうな目にあった状態のひとが竜宮に招かれて宝をもらうかたちは
日本などとも共通性のたかいものです。
かわいそうな目にあった状態のひとが竜宮に招かれて宝をもらうかたちは
日本などとも共通性のたかいものです。
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは
このこどこのこ竜宮のこ。「みい」さんです。
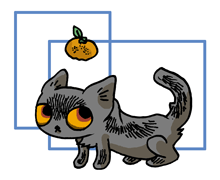
しかし、このねこが死んでしまったのでこれを埋めてあげると
そこからきれいな実をつけるの木が生えてきます。
実を食べてみるととてもおいしかったので
竜宮でもらったときからついてた「みい」という名前から、
その実を「みかん」と名づけ、それが蜜柑のはじまりになったんだソウナ。
このこどこのこ竜宮のこ。「みい」さんです。
正月の松かざりをくれたお礼だと言われて竜宮にまねかれた松売りのじいさんが、
おみやげとしてもらって来たねこ。
小判の糞をしたと言います。
じいさんの家はこの小判で豊かな暮らしが出来るように。
おみやげとしてもらって来たねこ。
小判の糞をしたと言います。
じいさんの家はこの小判で豊かな暮らしが出来るように。
しかし、このねこが死んでしまったのでこれを埋めてあげると
そこからきれいな実をつけるの木が生えてきます。
実を食べてみるととてもおいしかったので
竜宮でもらったときからついてた「みい」という名前から、
その実を「みかん」と名づけ、それが蜜柑のはじまりになったんだソウナ。
対馬に伝わっているもので「さんかん」や、
橘のはじまりの「りゅうぐうのくろねこ」(竜宮の黒猫)、
クガニー(シークワーサーの仲間)のはじまりになった「くがにのいん」は
ほぼ同じ型の柑橘類のはじまりのむかしばなし。
橘のはじまりの「りゅうぐうのくろねこ」(竜宮の黒猫)、
クガニー(シークワーサーの仲間)のはじまりになった「くがにのいん」は
ほぼ同じ型の柑橘類のはじまりのむかしばなし。
プロフィール
■雅号
氷厘亭氷泉(こおりんてい ひょーせん)
■ホームページ
■職業
イラストレーター
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
カテゴリー
最新記事
(01/10)
(01/09)
(01/08)
(01/07)
(01/06)
最新コメント
[01/24 دکوراسیون منزل]
[11/29 NONAME]
[05/08 100]
[01/13 佐藤]
[01/05 ひょ―せん]
アーカイブ
新・妖怪党 部署一覧
Logo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
最新トラックバック
フリーエリア
