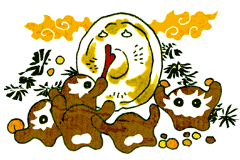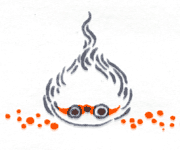氷厘亭氷泉の活動やラクガキをいろいろお届けしているブログです。
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは
あーあーみーちーなーがーさーんー。「かとくもんのぎんせい」さんです。
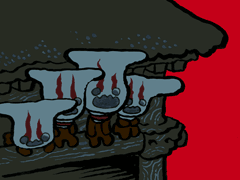
あーあーみーちーなーがーさーんー。「かとくもんのぎんせい」さんです。
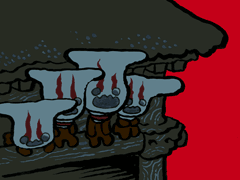
寛仁2年(1018)内裏の化徳門のあたりで
響き聴こえてきたというふしぎな吟声。
響き聴こえてきたというふしぎな吟声。
(化徳門は和徳門、花徳門、華徳門とも)
殿上人たちの耳にかなり入ったようで
みんななんだろう、なんだろう、とビクビクしたようです。
殿上人たちの耳にかなり入ったようで
みんななんだろう、なんだろう、とビクビクしたようです。
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは
モーゼとお呼び。「りゅうぐうのひきゃく」さんです。

モーゼとお呼び。「りゅうぐうのひきゃく」さんです。

竜宮から地上の人間へお礼などを知らせるときなどに
出動する連絡がかり。まさにそのまま、竜宮の飛脚です。
これが人間を案内する時は
周囲の海の水が割れて海の中でもふつうに歩けたソウナ。
出動する連絡がかり。まさにそのまま、竜宮の飛脚です。
これが人間を案内する時は
周囲の海の水が割れて海の中でもふつうに歩けたソウナ。
出雲の国などにつたわる
竜宮からたからものをもらう昔話に出て来るもの。
竜宮からたからものをもらう昔話に出て来るもの。
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは
新宿のあるお屋敷。「おがさわらのあずきあらい」さんです。
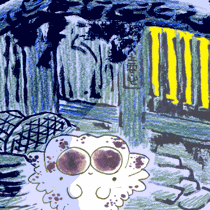
内藤新宿にあった小笠原という旗本の家に出たというもので、
小豆(あずき)を洗うような音をたてたといいます。
音がするなぁ、とその鳴ってるあたりに近づくと、
音はぴたりと止んだトサ。
新宿のあるお屋敷。「おがさわらのあずきあらい」さんです。
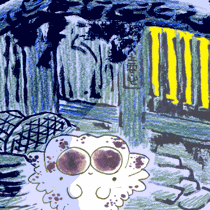
内藤新宿にあった小笠原という旗本の家に出たというもので、
小豆(あずき)を洗うような音をたてたといいます。
音がするなぁ、とその鳴ってるあたりに近づくと、
音はぴたりと止んだトサ。
周りでは蟇(ひき)の怪が起こしてるノダ、と言われたりしてたようですが、
小笠原どの自体はもう当たり前のようになってしまっていて、別に音を
怖いともなんとも思ってなかったソウナ。
小笠原どの自体はもう当たり前のようになってしまっていて、別に音を
怖いともなんとも思ってなかったソウナ。
プロフィール
■雅号
氷厘亭氷泉(こおりんてい ひょーせん)
■ホームページ
■職業
イラストレーター
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
カテゴリー
最新記事
(01/12)
(01/11)
(01/10)
(01/09)
(01/08)
最新コメント
[01/24 دکوراسیون منزل]
[11/29 NONAME]
[05/08 100]
[01/13 佐藤]
[01/05 ひょ―せん]
アーカイブ
新・妖怪党 部署一覧
Logo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
最新トラックバック
フリーエリア