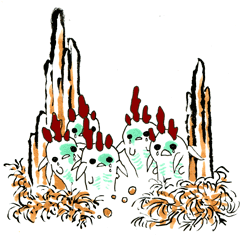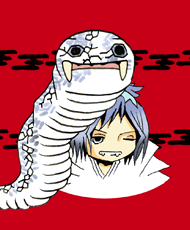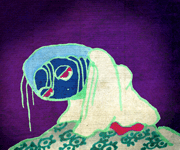氷厘亭氷泉の活動やラクガキをいろいろお届けしているブログです。
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは
ぴこぴこ、わしらの家だ、出て行け出て行け、「びゃくそかい」さんです。

『稽神録』などに見えるはなし、で、大陸にはちょこちょこと多く伝わってる
家に住みついて怪事を起こしたりする鼠(ねずみ)のおばけのひとつ。
むかし、蘇長史(そちょうし)というひとが引っ越して来た家は、
やたらと怪しいことが起こる凶宅でした。
しかし「そんなものはどうでもかまわん」と胆ふとく生活してたら、
夜に30人くらいの小さい道士がどかどかとやって来て
「この家から出てゆけ、さもなくばわざわいがふりかかるぞ」
と言って来たので、
「うるさいっ!」と叩き出したところ、
道士たちは逃げ去って竹やぶに消えてしまいました。
次の日、竹やぶを掘ってみると
白鼠が30匹くらい出て来たのでそれを退治したところ、
家に怪しいことは起こらなくなったんだソウナ。
ぴこぴこ、わしらの家だ、出て行け出て行け、「びゃくそかい」さんです。

『稽神録』などに見えるはなし、で、大陸にはちょこちょこと多く伝わってる
家に住みついて怪事を起こしたりする鼠(ねずみ)のおばけのひとつ。
むかし、蘇長史(そちょうし)というひとが引っ越して来た家は、
やたらと怪しいことが起こる凶宅でした。
しかし「そんなものはどうでもかまわん」と胆ふとく生活してたら、
夜に30人くらいの小さい道士がどかどかとやって来て
「この家から出てゆけ、さもなくばわざわいがふりかかるぞ」
と言って来たので、
「うるさいっ!」と叩き出したところ、
道士たちは逃げ去って竹やぶに消えてしまいました。
次の日、竹やぶを掘ってみると
白鼠が30匹くらい出て来たのでそれを退治したところ、
家に怪しいことは起こらなくなったんだソウナ。
PR
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは
隠れ笠をば横ちょにかぶり。「かくれかさのきんまる」さんです。

播磨の国の姫路にいる「おさかべきつね」の配下にあたる
「四天王 と ひとり武者」に名前を連ねてる狐のひとり。
この「四天王 と ひとり武者」は、井原西鶴の『西鶴諸国はなし』に
その名前が出て来ていて、その構成狐員のご芳名はイカノゴトシ。
・二階堂の煤助
・鳥居越の中三郎
・隠笠の金丸
・鶏喰の闇太郎
・野嵐の鼻長
こういったあだ名つきの呼び名の形式は、
絵巻物の『大石兵六物語』に出て来る狐たちにもあるもので、
この四天王の名前のつけかたから影響を受けてたりする
かもしれません。
(四天王 と ひとり武者 という風になってるのは大江山に鬼退治に出掛けた
源頼光の配下の武士たちの構成【渡辺・卜部・碓井・坂田+平井】を
そのまま採ってるからです。)
隠れ笠をば横ちょにかぶり。「かくれかさのきんまる」さんです。

播磨の国の姫路にいる「おさかべきつね」の配下にあたる
「四天王 と ひとり武者」に名前を連ねてる狐のひとり。
この「四天王 と ひとり武者」は、井原西鶴の『西鶴諸国はなし』に
その名前が出て来ていて、その構成狐員のご芳名はイカノゴトシ。
・二階堂の煤助
・鳥居越の中三郎
・隠笠の金丸
・鶏喰の闇太郎
・野嵐の鼻長
こういったあだ名つきの呼び名の形式は、
絵巻物の『大石兵六物語』に出て来る狐たちにもあるもので、
この四天王の名前のつけかたから影響を受けてたりする
かもしれません。
(四天王 と ひとり武者 という風になってるのは大江山に鬼退治に出掛けた
源頼光の配下の武士たちの構成【渡辺・卜部・碓井・坂田+平井】を
そのまま採ってるからです。)
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは
ほんとはいないかみさま、「つとめがつらいのしょうでん」さんです。

ほんとはいないかみさま、「つとめがつらいのしょうでん」さんです。

高輪山庚申堂(たかなわさんこうしんどう)にまつられているヘンな聖天さまで、
苦界づとめがつらくなっちゃうご冷験があります。
「高輪山庚申堂」は、『色街三十三詣』に出て来る一社で、架空の寺社。
「つらいの聖天」は「平井の聖天」(江戸の聖天宮のひとつ)の地口になってます。
プロフィール
■雅号
氷厘亭氷泉(こおりんてい ひょーせん)
■ホームページ
■職業
イラストレーター
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
カテゴリー
最新記事
(01/13)
(01/12)
(01/11)
(01/10)
(01/09)
最新コメント
[01/24 دکوراسیون منزل]
[11/29 NONAME]
[05/08 100]
[01/13 佐藤]
[01/05 ひょ―せん]
アーカイブ
新・妖怪党 部署一覧
Logo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
最新トラックバック
フリーエリア