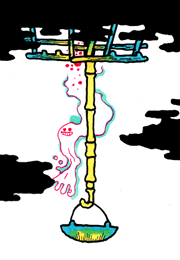かねをたべます。「かねをくうむし」さんです。

かねはかねでも、ならすかね。梵鐘をたべちゃう虫です。
伊賀の国の阿保村にでた、というはなしのあったふしぎな虫で、
何匹も何匹もあらわれて梵鐘を食べて食べて食べて
ボロボロ穴をあけてしまったんだトカ。
むかし、
ある男と恋仲になった娘さんがいたのだけど、
その娘の親がそれを大いにいましめて反発。
娘が恋人からもらった「鏡」を取り上げて、この梵鐘の材料として寄進してしまったのが、
そもそもの話なんだそうで、その娘のうらみが虫になって
梵鐘をモジョモジョ喰べたんだトサ。
かねにうらみはかずかずござるの、ヘビじゃない版ですね。
くちに入れてはいけません。「ようしつ」さんです。

蝿(はえ)の疾(やまい)と書いて「蝿疾」(ようしつ)であります。
うらみが蝿のかたちになって、ひとに重い病気をもたらし、
殺してしまったりしてしまうもの。
むかし、唐のころ、文宗(ぶんそう)という悪人が幽州の街道を歩いていたとき、
お経の紙を買いに行くとちゅうの僧侶を殺して金を奪ってしまいます。
その後、(20日後)
またそこを通りかかると、その僧侶の死体が腐りもせずそのまま転がってたので、
文宗は馬からおりてこれをベシンと策(むち)で打ったところ、
死体の口から蝿が飛び出して来てズバビューンと文宗の口へ飛び込んでしまいます。
吐き出そうとしてもいっこうにダメ。
ぜんぜん蝿は出てこずじまい。
その後、文宗は悪い風疾(ふうしつ)にかかって
一年しないうちに死んでしまったといいます。
無限発生・笠。「さんどぶち」さんです。
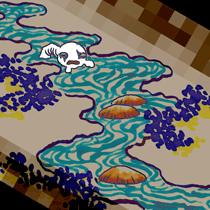
阿波の国の松尾川にあった淵。
むかし、川の上流でむらびとが集って博奕(ばくち)をしていると、
ひとりの旅の僧侶が「わしにも打たせてくれ」とその輪に参加。
すると余りにもこの僧侶が強い。みんな大負け。
そこでむらびとたちはこの僧侶を帰り道で待ち受けて捕まえ、
松尾川にドブン。殺してしまいます。
その後、この僧侶を殺した日になると、淵のあたりから
ふしぎと僧侶がかぶっていたのと同じ形の三度笠が
ぞくぞくと流れて来るようになったそうで、むらびとはそれを恐れて
法要をするようになったんだトサ。
川・坊さん・「なにをしとるのかね」という展開のせいで
一瞬、「いわなぼうず」(岩魚坊主)とかの系統(「毒流しはやめなされ」)なのかなと思ったら
かなり違う角度から攻められたので、はじめて読んだときは
「こう来たか」という感じでした。
――僧侶とか六部とか座頭とか旅人を殺しちゃう系統のひとつなのですね。
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
Logo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党