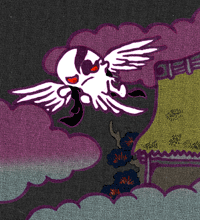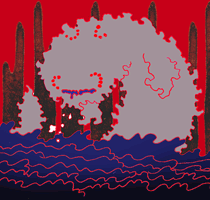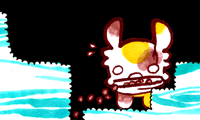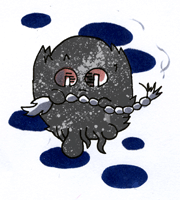ほうきを粗末にしちゃイカン。「ほうきねぶと」さんです。

ほうきの上をまたいだりすると、ほうきの精霊とか神様のばちを受けて
体にボチッと発生するよ! といわれていた癰疽(はれもの)で、
周防大島などで言いならわされていたものです。
ほうきを大事にしなかったり、敬意をはらわなかったりすると
何かしらの罰をうけるよ!(ex.火事のときに逃げられなくなる、お産が重くなる)
というのは、全国区で立候補されている俗信のなかの有力選手ですが、
これはもともと、ほうき、っていう道具自体が一般的な道具じゃなくて
神聖な行事のときにだけ使われる特別な道具だったから、だ、と、
よく説明されているので、まぁ、そんなに深く説明しくてもいいか、と多少なげやり。
レパートリーはちよよろず。「うたしりのへび」さんです。
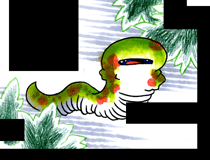
この世にある様々な歌を知っていて、
それを日々うたってたという目玉のないへび。
むかしむかし、ある日のこと
「へびさん、へびさん、あたしゃ、うたを歌いたいのでおぼえたい」
こんな風にみみずが頼んできたので、
「教えてやってもいいけど、これは大事なもんだ、ただとはいかん」
と、へびはみみずの「目玉」と自分の「歌」とを交換した為、
これ以後、みみずたちには目玉がなくなって地面の中でうたを歌うようになり、
へびたちには目玉が出来て出歩けるようになり、うたは歌えなくなってしまったんだソウナ。
と、いうむかしむかしの蛇のおはなし。
イルカ避け装置。「がんじゃいわ」さんです。

沖縄の今帰仁村の港につたわる大きな岩で、
これが立ってることによって、この近くにはイルカが来ないと言われていました。
むかしむかし、この港にたくさんのイルカがやって来たとき、
あたりのひとは「イルカのむれだ!とりに行こう!!」と大勢で大寄せ。
ところが、その人群れにまじってイルカをもらいにいったある娘さんが
雑踏の中で死んでしまいました、悲しみくれたお母さんが、
「この海にもうイルカたちは来るな」とうらみを込めて投げた小石が
この大岩になった、などといった昔話が残っています。
「がんじゃ」の意味はよくわからない、と島袋厳七の文には書いてありました。
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
Logo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党