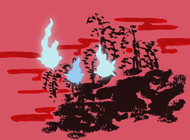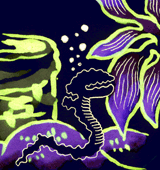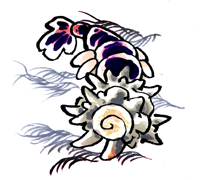氷厘亭氷泉の活動やラクガキをいろいろお届けしているブログです。
本日の「和漢百魅缶」アップは、今年3度めのお酉さまということで
また、また、また、バード。「でいきゅうこうちょう」さんです。

また、また、また、バード。「でいきゅうこうちょう」さんです。

水の底などから稀にプカンと出てきたりするというふしぎな泥んこだまで、
コンクリートでも化粧して日焼けさせたじゃないか、ってくらいに固いのですが
道具(岩でガスンガスンやる、のみでぶち欠く、ドリル的なもの…などなど)
を駆使してあけてみると、その中には黄鳥(ほととぎす)が入ってる、
というのがコチラなのでございます。
岩石や泥んこだまの中から鳥とか生き物が出て来る、というのは
大陸に多く伝わってるもののひとつで、
それこそ、マリオワールドに出て来るシャボン玉に入った
クリボンやボム兵みたいにあっちこっちに例があるものです(大言壮語)
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは
肉屋の商売あがったり。「じつ」さんです。
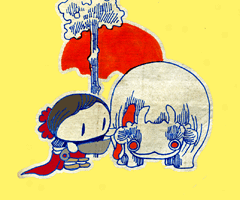
肉屋の商売あがったり。「じつ」さんです。
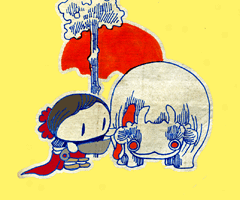
西域にあるお国、大月氏の地にいると言われていたふしぎな牛。
少しずつ肉を取るだけだったら、次の日にはその部分が治っていて、
永久にお肉が採れるというものでございます。
なんともふしぎなこの「日」(じつ)さんですが、『元中記』には、
大月氏のひとが
「おらんくの牧場には、肉がいくらでも採れる【日】っていう牛がいる」
という話をしたら、漢土のひとが、それに対抗して
「中華には糸を出す【蚕】っていう指くらいの大きさの虫がいる」
っていう話をしてお互い「すごいだろ」って顔をしたけど
お互い「そんなへんなもんいるわけねーだろ、ケッ」と腹の中では思ってたよ
というお話が載っています。でも、かいこが実在するんだから
この牛さんも、実はちゃんといるのかも知れませんがな。
プロフィール
■雅号
氷厘亭氷泉(こおりんてい ひょーせん)
■ホームページ
■職業
イラストレーター
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
カテゴリー
最新記事
(01/13)
(01/12)
(01/11)
(01/10)
(01/09)
最新コメント
[01/24 دکوراسیون منزل]
[11/29 NONAME]
[05/08 100]
[01/13 佐藤]
[01/05 ひょ―せん]
アーカイブ
新・妖怪党 部署一覧
Logo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
最新トラックバック
フリーエリア