氷厘亭氷泉の活動やラクガキをいろいろお届けしているブログです。
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは、
雨ぼっぼっ。「ちゃわんむしのちゃわん」さんです。

雨ぼっぼっ。「ちゃわんむしのちゃわん」さんです。
茶碗蒸の中身を食べたあと、そこへ直接
お茶をいれて飲むのはよくないとされてて、
それをすると結婚式や葬式など
人生の大事な場が大雨になると言われてたりしました。
お茶をいれて飲むのはよくないとされてて、
それをすると結婚式や葬式など
人生の大事な場が大雨になると言われてたりしました。
出がけにお茶づけを食べることや、
赤飯にお茶をかけて食べたりするのをきらう内容の俗信と隣接してる例。
赤飯にお茶をかけて食べたりするのをきらう内容の俗信と隣接してる例。
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは、
「たがのしろざる」さんです。
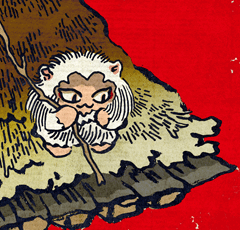
「たがのしろざる」さんです。
近江の国の御上嶽の陀我大神という神社にいた
小さな白い猿(さる)で、近くのお堂に恵勝(えしょう)という修行僧が来たときに
「どうか法華経をわしのために読んでくれ」と
頼みにやって来たことがあったと語られてます。
小さな白い猿(さる)で、近くのお堂に恵勝(えしょう)という修行僧が来たときに
「どうか法華経をわしのために読んでくれ」と
頼みにやって来たことがあったと語られてます。
この猿はもともと東天竺の国王で、生前に修行僧に対して
「1000人もの従者を持ってるのは農業の妨げである」と禁じたことから、
善道を妨げた悪報として猿の身に生まれてしまったのだトカ。
「1000人もの従者を持ってるのは農業の妨げである」と禁じたことから、
善道を妨げた悪報として猿の身に生まれてしまったのだトカ。
『日本霊異記』の「依妨修行人得猴身」にあるはなしで、
陀我大神はこの猴の名前だともされます。
仏法の修行や善道を妨げた者は猿に生まれると語ってる内容。
「陀我」は「多賀」のことだもといわれてます。
陀我大神はこの猴の名前だともされます。
仏法の修行や善道を妨げた者は猿に生まれると語ってる内容。
「陀我」は「多賀」のことだもといわれてます。
プロフィール
■雅号
氷厘亭氷泉(こおりんてい ひょーせん)
■ホームページ
■職業
イラストレーター
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
カテゴリー
最新記事
(01/11)
(01/10)
(01/09)
(01/08)
(01/07)
最新コメント
[01/24 دکوراسیون منزل]
[11/29 NONAME]
[05/08 100]
[01/13 佐藤]
[01/05 ひょ―せん]
アーカイブ
新・妖怪党 部署一覧
Logo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
最新トラックバック
フリーエリア
