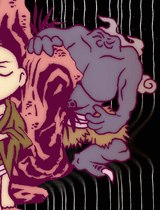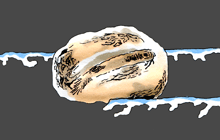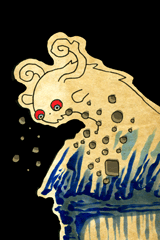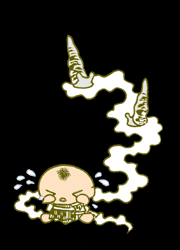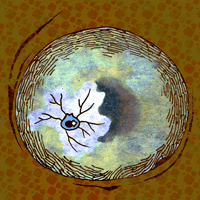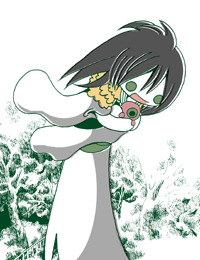ひっこしものがたり。「あんおうしだ」さんです。
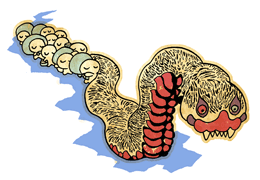
洪の翠巌(すいがん)にあった
斉の安王(あんおう)のほこらに住んでたぬしで、とても大きな大蛇。
むかし、死心(ししん)という和尚さんがこのほこらの近くの寺にやってくると、
ここが異常に人民たちからもてはやされてる淫祠になってたので、
これをつぶして寺の脇にうつし、ほこらの跡地には庵をむすんで自分が住んでしまいました。
すると死心が眠ってるときにぬしが大蛇のすがたで出没。
しかし死心が大声で一喝したところ逃げて行ってしまいます。
次の夜は神のすがたで現れて
「余はもはやこの地に安住できぬ、ついては広南にひき移るによって
60人ばかり人手がほしい、そのことぜひ御諒承くだされ」
と言ってきたので死心はそれを許可します。
すると翌日、寺でつかってる壮夫たちが疫病にかかってばたばたと急死。
その数はちょうど60人だったといいます。
アイヌからツンツンツン。「カニツンツンピィツンツン」さんです。

アイヌにつたわるもので、「カニツンツンピィツンツンカニチャララピィチャララ」
という珍無類な鳴き方をしていたふしぎな鳥。
「おちちんぷんぷん」など、本州以南の各地にも分布してる
めづらしい鳴き声の鳥をたべちゃうはなしとおなじ種類のおはなしです。
パナンペ(むかしばなしに出てくる定番のひと)が山へ木の実を採りに行くと、
この鳥がくちの中にとびんこんできてゴクン。
すると「カニツンツンピィツンツンカニチャララピィチャララ」と
鳴き声そっくりのおならを出す体になってしまい、
ついにはそのふしぎな音色をお殿様にほめられ、ご褒美をたまわりましたんだトサ。
パナンペの真似をして大きなおならで殿様からご褒美をもらおうとしたペナンペは、
たべものの食べすぎで下痢をしてしまい、家臣たちに斬られて殴られて
血まみれになってしまいます。
除草剤の必要のおや。その2。「こうしんさまのあまんじゃく」さんです。
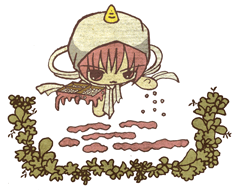
磐城の国、草野村北神谷などにつたわる「あまのじゃく」。
むかし「百姓たちがなまけてる」とそこらじゅうに雑草の種をまきちらして
田畑に雑草が生えるようにしてしまったので、庚申様(青面金剛)がこれに激怒
二度と動けないように今も足の下におしつぶしてるんだトカ。
庚申様をまつると作物の出来が豊かになるという俗信に連結してます。
その2、とつけたのは、その1として駿河の国などに伝わる
「あまんじゃく」(お釈迦さまの言いつけをルーズに施行して雑草をつくった)を
アップしてるからであります。
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
Logo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党