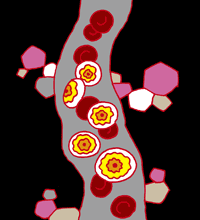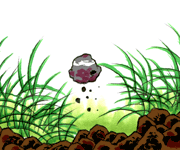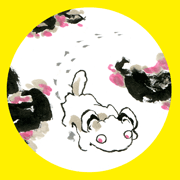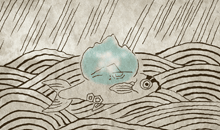氷厘亭氷泉の活動やラクガキをいろいろお届けしているブログです。
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは
ただひとつものごみは許さじ。「ふんじけぇのぬまのぬし」さんです。

ただひとつものごみは許さじ。「ふんじけぇのぬまのぬし」さんです。

陸奥の国は東通村の下川代にある
「ふんじけぇの沼」に住んでる主で、
おんなの姿をしてると言われてます。
大変きれいずきな性格なだそうで、
雨が降ってこの沼に葉っぱや枝やごみが流れて来て
水面に浮かんでたりしても、次の日にはきれいさっぱり
ひとつも残らず無くなってたと言います。
「おなごは入るな」と言われてて、女のひとがこの沼の水に入ることは
主が怒るから、ということでかたく避けられてたそうです。
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは
名のきこえたる。「かきのきさま」さんです。
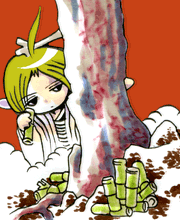
榎戸貞治郎が『民間伝承』に寄せてる報告によると、
大正10年ころ、神社の本殿の位置をすこしさげる工事にかかったところ
この柿木様の枝が屋根にあたっちゃうのでなんとかならないか、と
問題になって村のひとたちが「どうしたものか」と困ったそうですが、
数日後には、柿木様の屋根にあたりそうだった枝がぜんぶ
そろって上向きに延び進んでて、枝を伐らずにすんだ、
――というふしぎもあったそうです。
名のきこえたる。「かきのきさま」さんです。
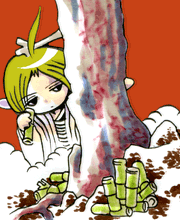
下野の国の都賀郡、絹村にある高崎神社の近くに生えてた柿の木で、
この木に竹筒をおそなえすると耳の病気が治るとか、
木の下の土を疣(いぼ)にぬると治るなどと言われてました。
願掛けをきいてくれるありがたい柿の木なので、
この木の実を採って食べちゃいけない、などとも言われてたそうです。
榎戸貞治郎が『民間伝承』に寄せてる報告によると、
大正10年ころ、神社の本殿の位置をすこしさげる工事にかかったところ
この柿木様の枝が屋根にあたっちゃうのでなんとかならないか、と
問題になって村のひとたちが「どうしたものか」と困ったそうですが、
数日後には、柿木様の屋根にあたりそうだった枝がぜんぶ
そろって上向きに延び進んでて、枝を伐らずにすんだ、
――というふしぎもあったそうです。
プロフィール
■雅号
氷厘亭氷泉(こおりんてい ひょーせん)
■ホームページ
■職業
イラストレーター
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
カテゴリー
最新記事
(01/12)
(01/11)
(01/10)
(01/09)
(01/08)
最新コメント
[01/24 دکوراسیون منزل]
[11/29 NONAME]
[05/08 100]
[01/13 佐藤]
[01/05 ひょ―せん]
アーカイブ
新・妖怪党 部署一覧
Logo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
最新トラックバック
フリーエリア