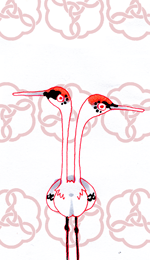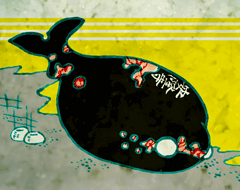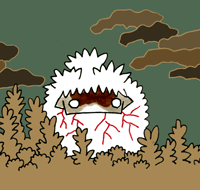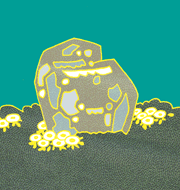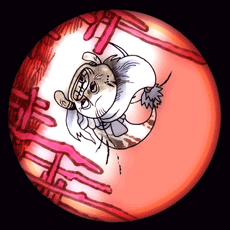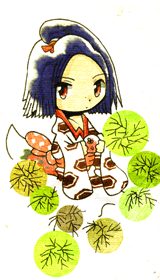ミリオネアめおと。「がじゃがじゃ」さんです。
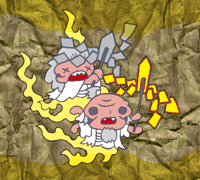
芸州の蒲刈に伝わるもので、真夜中になると
金と銀の御幣(ごへい)を振り回しながら
「がじゃがじゃがじゃがじゃ」と声をたてて
家の中を大きな音を立てながら走り回ったりしたというおばけ。
実は、ものすごい大金持ちだったじいさまとばあさまの霊で、
自分たちが死んだあと、埋めたままになってしまってる大金のありかを知らせたいため、
死後空き家になってしまった自分の家に出てたというもの。
「がじゃがじゃ」(金じゃ金じゃ)とアピールしつつ出てたわけですが
みんなその「がじゃがじゃ」を怖い叫び声だと思ってたという裏目の結果に。
「かねのばけもの」などに近いおはなしです。
キップかってね。「きしゃのかいそう」さんです。
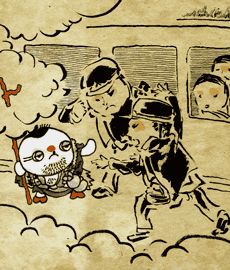
大正のはじめごろ、
周防の国の下松駅に現われたことがあったというもの。
ぼろぼろな着物を着たきたないお坊さんで、
「銭がないので、無賃で汽車に乗せておくれ」
と駅員に話しかけて来たので、
「そんなのはいかん」
とおことわり。何度たのんでも駅員が首をたてにふらないので、
「では乗らぬ、そのかわり汽車も動かぬぞ」
と言い捨ててお坊さんはいなくなってしまったそうですが、
その後、汽車が発進しなくなってしまい、駅員たちはびっくり困ったトカ。
瓜をわけてあげなかったら
瓜をぜんぶとられてしまった徐光の話や、
弘法大師にいじわるしたら、芋が石になったとか、
しぶい柿しかとれなくなったとか、井戸が涸れた、といった話に近いもので、
道具立てがモダンになったものでござるな。しゅぽっぽー。
ジャストアモーメント。「かんぼういぎのばけもの」さんです。

甑島のかんぼういぎという場所に出たというおばけ。
むかし、薪を求めてあがってきた漁師たちが
このあたりを歩いてると、死体が転がっててびっくり。
急いで舟に戻ったところ、おそろしげな女が岸壁で
「待てー」と叫んでたんだトカ。
船乗りさんたちが、どこかに上陸したり停泊したりして
あやしい女の妖怪からききいっぱつ、逃げ切る、というのはいくつか確認されていて、
「だいとうがはなのばけもの」や「だきのばけもの」などと近いものだす。
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
Logo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党