「くじらなヤツいなんかいないのー?くじらー」という声が楽屋であがったので
アイヌの昔話の中からガサゴソっと「フムペフッチ」さんです。
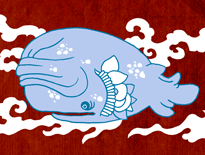
あちらの言葉で、くじらばあちゃんという名前のこちらさん。
パナンべとペナンべが出て来る昔話のなかでは
(アイヌの昔話に出て来る太郎冠者、次郎冠者みたいなひと)
「おぅ、ばあさま、くっついてるシラミをとってやるよ」
と、言われて、パナンべ・ペナンべに首のお肉をたべられてしまい大激怒。
ふたりをどこまでも追っかけてくるという
かなりハードなアクションをくりひろげたりします。
パナンべは、狭い谷道に逃げ込んでセーフ。(ばあさんせまくてとおれない)
ペナンべは、広いほうをえらんじゃってアウトー。(ばあさんおいつきデストロイ)
なかなか、サスペンスな展開。
5月8日に
連続興行で「和漢百魅缶」アップをしたかたがたの
一束まとめのツヅキでござい。
それにしても、文量おおいなー。まったくもぅ。
▼しおうりじんくろう/らぎょうせんにん
7日の主任は沼や池の主、と、ブクブクシ沈むものでしたので、浮かぶものの対幅。
裸形仙人の話は、いっしょに日本に来たのに、プイっと帰っちゃった他の人も気になる。
▼もりび/ほけきょうどうのけちび
浮かんでとんじゃうものとくれば、光るひのたまの対幅。
法華経堂の怪火は、正体みきわめてやるぜ、と挑んで逆にへこまされるパターン。
▼らいがのびょうぶ/だいひょう
光るものはどこにでる、空にでる。というつながりかたでつづきは気象の対幅。
こげがうまい具合に旭と雲海になったという雷画の屏風……禅画の領域だネー。
▼こうかもんのりきし/すごうがば
ここでは、そんな雷画の屏風からの連想で、名品からぬけだした!という対幅。
皇嘉門の力士はただのいやがらせとしか考えられません。迷惑防止条例違反。
▼ばけべんてん/そでもぎさん
名品からぬけだした……ような美人、とかいうつながりで、美姫麗媛の対幅。
化弁天さんは、なかなかお茶目さん。こういう神様っていいなぁ。
▼ほぎのだいじゃ/しもくらのおろち
姫君といっしょに昔話によく登場するのは神代のむかしから蛇。スネークな対幅。
保木の大蛇、下倉の大蛇、精進池の主、南瓜蛇、火口縄…蛇もののチョイス多かったかな。
▼かえるいし/おほりのおおすっぽん
へびは水神さまだから、水に縁のあるあたりから、お堀にまつわるふたつを対幅。
帰る石は、「ご普請がすめば帰るよ」と言って帰れなかった大工たちの「かえる」だトカ。
▼やいばのきじ/アプトルヤムペウェンユク
お堀の表面にキレイな波をえがきあうのは川風。風にまつわる対幅。(ちょっとキビシイ)
刃の雉は馬琴の『復讐奇談小夜中山』の登場怪物(笑)で、昔話では蛇身鳥とかいう名。
▼ぼっかあさん/しんしょうき
風…かぜ…ふう…フー…フード!! という強引っぷりで食べ物に関する対幅。
渤川さんのような「年末にお餅をつくらない」という習慣を説明する昔話は全国種々雑多。
▼いまかぼし/うらみちむし
さぁ、休憩。オリジナルさんの中からです。
7日の新「なうなう」以外は2008年にデザインしたものの中からの蔵だし。
▼こうじゅん/ねずみいし
食べ物にちょっとかぶりますが、こちらは土や石と食べ物が関係してるものの対幅。
蛟筍は土の中からたべものを採る。鼠石はたべものを盗り石の中へ。
▼やつあしのうさぎ/れいだんぎょく
いやぁ、どちらも土やら石の中の珍しいものでしたねー、といって次は珍物の対幅。
八足兎は、兎は陰獣でその足が陰の極数である8ですから…などとうるさい解釈もある。
▼うえきおばけ/きくぼとけ
珍物もよろしいですけど、ほらごらん、野菊のようななんでもない植物もキレイな対幅。
植木お化けは何個も絵草紙などで描かれてますが、とりあえず勝川春英のものから。
▼りゅうせん/こうじゅけつ
キレイなものでもこの世のなかでものを言うはゼニカネよ。お金やお珠の対幅。
流銭の話は、結局のところ、だれかがぬけがけして瓶ひろいにいったダケかも。
▼かげむし/あぶらむし
お金のためにこのわたしゃ、苦界の泥に身をしずめ。ベベン。遊里に関する対幅。
膏虫は膏血虫っていう字で書かれてる雑文も見つけたりしました。世界のゴミ虫です。ほろびよ。
▼ささがみさま/おたのかみさま
お金だの遊里だのなんという堕落した方角ですか!との修正軌道でぺカっと神様の対幅。
笹神様をまだやってる地域ってのは僅少らしい。そういえば地元のこういう行事も滅亡寸前だもんなぁ。
▼ごばんなみ/どうちゅうどうし
神様が好きなものに御祝儀があります。ごしゅーぎ。ごしょーぎ。はい、碁と将棋の対幅です。
碁盤波の北条の家紋、ピンとこない方は『ゼルダの伝説』のトライフォースを想像してくださいアレです。
▼たなかのひのたま/たくろうび
――などと、いろいろこじつけて関連テーマをつなげてたりしました。
だんだん真打にちかづいてきました、ということで、華やかにおごそかに。光火の対幅。
焚朗火の後鳥羽天皇の歌にある「たくひの里」というのは隠岐の焼火権現のあたり。
▼ごいぞう/まだいこ
ラストの前は「ひざがわり」ということで、かるくひらがなな名前で対幅。
まだいこは、既にアップしてある間太皷と実質は同一種ですが、ま、いいや。
がらっぱとがらっぱどんの違いみたいなもんです。(ひらきなおり)
▼ゆじ
7日、8日と、いままでアップの運行びかえしてた分のイラストを
連続興行のかたちでアップしたわけですが、今後もグイっとみなさまの運向きが
アップしますように、覇王が世にでるとあらわれるという登山の神様、
兪児を、主任にすえさせていただきました。
一挙に75枚はなかなか見るのもお骨おりでしょうが、
まぁ、ゆるゆるとご笑覧たまわりますれば、うれしい次第でゴジャマッスル。
連続興行で「和漢百魅缶」アップをしたかたがたの
一束まとめでござい。
(「いっそく」って変換しようとすると出ないな……ぶつぶつ)
アップの順番をじーっと見ていた方のなかには
ナントナクきづいてた方がいたかも知れませんけど、
例によって、例ノゴトク、『蒙求』(もうぎゅう)っぽく
関連性のある一対ごとに並ばせてアップをしたので、
そんなところに触れつつ、ズラーーーーーーーーーーーーーっと。
▼くびばかりのばけもの/ななつくび
連続興行のはじまり、首位にスタートということで、首なおばけの対幅。
首ばかりのばけものは『古今百物語』にある挿絵をリデザインしました。もとも結構とぼけた図。
▼てんぐづか/みのおさんのてんぐ
首の真上は鼻の下、ということで、天狗にまつわるものの対幅。
箕面山の天狗は撃たれたときのキズを人間に化けて有馬温泉に湯治しにいったりしてます。
▼こんごういんのあし/なまくびさがり
盛者必衰のことわりをあらわす。あがったらさがれ、ということでぶらぶら下がる対幅。
金剛院の足は、江戸の本所とか番町に伝わる「足洗いやしき」そのまんまなお仲間。
▼かぼちゃのへび/しょうがのによいごえ
ぶらぶらさがるはカボチャの実、とつながったところから、ベジタボー!な対幅。
ショウガだいすき!ジンジャーエールだいすき!ガリだいすき!
▼ぎょふくのかがみ/しせき
たべたら入るよお腹の中へ。ということでお腹の中から目撃ドキュンな対幅。
『稽神録』に載ってる紫石の取得者・陳さんは、孫が酔っ払って石を割っちゃって斜陽しました。
▼よはちのよめ/おにのあぶら
お腹の中には鬼が居る。(節分のときよく言われるコトヴァ)つづくテーマは鬼!でこんな対幅。
与八の嫁っていう呼び名は、なかなかもって妙に味のある呼び名。
▼たいとうがはなのばけもの/しらんばがたけのねこ
鬼はたびたび化けますドロロン。ということで、海と山の、人間に化けるおばけでこんな対幅。
大唐が鼻の化物は「あやかし」って紹介される時が多いけど、読んでみたらそうでもなかった。
▼なうなう/そりかえし
中入り休憩なコーナー。オリジナルさんのなかからの対幅。
チャットで話題が出たせいで、ついに最近の「なうなう」が加入してしまった。
▼ほいほいどん/よびさか
人間に化けるおばけは、ひとに呼びかけてきます、ということで人を呼ぶかたがたを対幅。
呼坂に出て来る左近将監は、神社を焼き討ちしたりしたのが原因で罰があたったんだとか。
▼ごかんのたゆうきゅうのあつがり/ほぐちなわ
じゃあさー、声を使わず人を呼ぶ方法は? 煙火(のろし)。 ということで火に関係ある対幅。
火口縄がのってる『襍土一覧』は、京都の本なので、太夫子国は吉原じゃなくて島原?
▼たておべす/おおやまめ
火の対抗馬は水でござる、ということでスイギョノマジワリ、おフィッシュの対幅。
あ、立蛭子は、魚類じゃなくて哺乳類か…ま、いいや。「たてえぼし」っておばけもこの仲間らしい。
▼おりづめぬき/おはぐろばばあ
魚にお水、おミズは狐(芸者)狸(幇間)というわけで狐と狸をコンポコっと対幅。
お歯黒婆の出現によって、お歯黒シリーズのレパートリーが増えました。
▼がわんばっちょ/コヌプキオトグル
おミズはふわふわ川端やなぎ。川にまつわる対幅でござんす。
がわんばっちょ、って音の響きがとんでもなくパワフル。河童の中では相当パワフル。
▼どうらくじぞう/かめさま
川といえばお地蔵さま。(――このへんから飛躍がとんでもなくなります。
片岡春香センセイもご推薦の百科事典の中に、町のうつりかわりというページがあって
そこに出てくる架空の土地の話の中に川でおぼれた子をまつったお地蔵さんが
過去から現代への土地のうつりかわりをかわらず眺めてるという設定で出て来るのです)
というスペシャルぶっとびによって、お地蔵さん的な信仰対象物の対幅。
▼とうたぬし/げんたぬし
信仰の対象をたよるよりも、自らがそんな対象になっちゃった仙人の対幅。
この藤太主と源太主、浄蔵という坊様が川を渡れず困ってると丸太を山から呼んでくれたとか。
▼けいそくそう/けいそう
男の仙人が集合するところは東王父のところ。ことで東天紅(とーてんこー)な鶏の対幅。
鶏窓は『蒙求』から採った呼び名。リアル対句は簫史の簫に鳳凰が寄ってきたという「簫史鳳台」
▼ようめいかい/ひだるぼう
鶏が鳴きます朝はまず、ごはん食べなきゃ動けません。食べることに関する対幅。
姚明解さん、地獄にいるくせに結構ひんぱんに友達のもとに出て来てます。地獄って実はひま?
▼ほろどぬまのぬし/しょうじんがいけのぬし
「食べる」といえば「飲む」。昔話で人や者をのみ込んじゃう沼や池の主さまの対幅です。
「ほろど沼」ってなかなか思いつかない地名ですね。やっぱり北奥羽にはこういう地名が多い。
サイト容量調整とタグの変更作業、見やすさの向上工事を展開のため、
アップの作業が一時お休みとなります。わう。
「苧うに(おうに)」とか「うわんうわん」とか言う名前がついて
絵がのこされているものの、モトのほうをたどっていくと、
こういう名前が基本だったのかな? と思われる
狩野家に伝わるデザインおばけさんのおひとつ。
ですが、
最近、妖界東西新聞で何回か登場してる「おとろし」の「音呂志さん」や、
すでにアップされてる「うわん」などと同様に、
こっとんきゃんでいでは、こんなに女のコ女のコなおデザインに。
なっとります。

「和漢百魅缶」、工事作業します、とは言っても
別にページのリンクを抜いたりせず、に、
替えの作業が出来た所からタグなどは更新してゆきますので、
フツーに見物なさる分には、いつもと同様、差しさわりありません。
いままでどおりサランパァ~とご覧下さい。
歌舞伎座の改造工事よりはお時間かけませんので。
へぃ。
ほんとは昨日(2月22日)に「2020」とうたつ!! だと
なんだか数字がイイ具合~、になったんでしょうケド、
まぁ、そこいらへんはイイです。
「2222」とうたつ!! を狙ってたら、
十二指腸が大ジャンプするほど苦しんだでしょうケド。(笑)
食物連鎖のうずの中へ淘汰されました。(笑)
そんな本日の「和漢百魅缶」は、食物連鎖というフレーズを活かしつつ?
ハンティング、フィッシング、「つりおんな」さんです。
むかし、ある池の中に、両手おっぴろげた以上の
デカさをほこる巨大な魚、つまり、ヌシですな、
そんな魚がいるですよ、などという噂をみみにして、
ある釣り好きの男が、
「よし! オレがいっちょゲッチューしてやるか」
と、考えて、つり道具をかかえてエッチラオッチラ、
池について、糸をたらして、じーーーーーーっ。
やった! 糸ひいてる! ひいてる!
――と、急いで上げたそのサオの、先に浮かんだその影は、
巨大なサカナ、ならぬ、華麗なビジョ。
糸の先に釣り上がったその美女が、
いきなり顔を前に向けて、ニッコリとほほえんで来たので
男はドギモをぬかれて、サオ放り出して、
自分の家まで猛逃走。
戸をとざしてガタガタ震えていたそうですが、数日後にぽっくり。
ヌシを釣ろうなどとは考えぬことじゃ、という昔話。

昔話中に、固有名詞な呼び名は無かったので、
おんなのこが釣り上がる、ってところからの連想連環で
歌舞伎の松羽目物(狂言をモトにしたお芝居)の演題から
字句を持ってきて、項目名に致しますた。
どんな大きな版面でも光速に取り込める
絶大なる画像スキャン技術がポンっと開発されないものじゃろうか、
などと妄想しつつスキャナーを駆動させてますが
本日の「和漢百魅缶」のアップさまは
ねんねんころりよ、「ねんねんぐ」さんです。
赤ちゃんの泣き声をするおばけ、といえば
大著名なところで「こなきじじい」とかがいますが、
こちらのキツネさんも、そういうワザで
人間をビックリシャックリさせるお方。

夕暮れも進んであたりがうすぐらくなって来たころ、
山の中を歩いているひとの耳の中に、
赤ちゃんが泣いてる声や、それをあやして歌ってるような人の声を
うっすら、ぼんやり、ときどき、はっきり、響かせて
うすら寒い気分にさせましたとか。
その時のこもり歌の声が「ねんねんぐー」と聴こえるので
こんな名前で出ています。
ファックスの紙送りのズズズズ…って音が
エキサイティングに鳴るような気がする昨今です。
とか言いつつ、本日「和漢百魅缶」にアップしますのは
出たり入ったりかくれんぼ。「ほうそうのみや」さんです。
越後につたわるもので、
四角いお宮のなかに、イタチみたいなのが
何匹も何匹もすみついていて、
そこに出入りしている姿が急に見えなくなったなぁと思っていると
どこかで疱瘡(天然痘)が流行して、
これがお宮に出入りしてるのが見られるようになるのは
その流行が終息してるのと同じぐらいのタイミング、
ということがあったことから、
疱瘡をもたらす疫病の神様の使いなんじゃないかと
思われて、「ほうそうのみや」と呼ばれるようになりましたんだトカ。
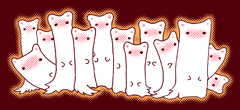
描いてると、ペット屋さんのフェレットコーナーにただよう
あの香りのイメージがお鼻にいっぱい。もりだくさん。(笑)
こんなもんだろ、と目分量でお湯をいれたら
なっかなっかのドロンドロンっぷりで、
コップをかたむけても、口に届くまでが、のたのた鈍行列車でした。(笑)
のったのったと進むといえば、てなことで本日の「和漢百魅缶」は
うみへび様でござります、「うじゃ」さんです。
しっぽの先にパープルにきらめく宝珠がついてる、
という海蛇で、これが現れるのは豊年のしるし、というもの。

しっぽに宝珠が付いとります、というのは、
弁天さまをまつっているお宮などに飾られてる
図像とか絵馬とかにある白蛇の絵にもあるものですが、
豊年の予言がありました、とのフレコミで売り出されたりしていた
「神社姫」の画にある、しっぽの先っちょの剣みたいな形の物も、
こういったものと関連性の深いものなんでしょうナ。うん。
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
Logo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党




