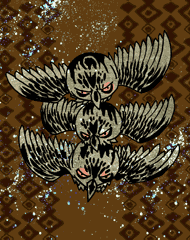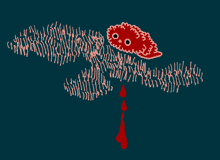柚にうらみあり。「おびこさん」です。

備後の国の東城につたわるもの。
子供の夜泣きが激しいときなどお参りすると
よく効くといわれてました。
むかし、この地にあったお城が攻め落とされたとき、
逃げ延びた乳母と若殿さまが追っ手から隠れるために
生えていた柚(ゆず)の林にむかって
「どうぞ隠してください、若様のいのちをお守りください」
と頼んだのですが、この柚の枝がガサゴソ動いて
隠れてたのが露顕、追っ手のさむらいたちによって
ふたりは殺されてしまいます。
その乳母と若様をまつったのがこの「産子さん」(おびこさん)で、
ガサゴソ枝が動いたのを恨んで、この地域には
これ以後、柚の木は生えなくなったといいます。
鳴きます鳴きます。「くろくちこい」さんです。

筑前の国の十石山につたわる鳥。
「りょうしこい、くろくちこい」という声をたてて
山の中を飛び回ってるといいます。
むかし、山に狩りに来た武士がひと休みしてたところ、
連れてきていた黒口(くろくち)という犬が
飛び掛ってくるような剣幕で吠えまくります。
「わしを喰い殺す気か」
と思って鉄砲で撃ったところ、黒口は跳ね上がり、
近くにひそんでた大蛇を咬み殺して死にます。
犬が大蛇に気づいて吠えてたと知った武士は、
自分の短慮を恥じて犬をとむらったあと、山で自害をしてしまいます。
そのことを村人づてに聴いた武士の妻が、悲しみながら山に来て
「りょうしこい、くろくちこい」と泣いているうち、鳥になってしまったんだトカ。
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは
亥の日ナイトにおどりまくれ。「ふくがいる」さんです。

「ふくがいる」というのは「ひきがえる」の転訛で、特に固有名詞ではないようです。
摂津の国、豊島郡北豊島村につたわるもの。
10月の亥の子の日に来る「ひきがえる」で、
家々をまわって家でごろごろりんところがったり
手ぶり足ふり踊ったりしていったといいます。
大正のなかばくらいまで村では行われてたそうで、
むしろを2枚つないだものをかぶって目の穴をあけたものをかぶって
2匹ぐらいの「ふくがいる」に子供達が扮しておこなってたそうです。
「ふくがえる」になった子供以外のこどもたちは、
竹をわらでつつんだものを持って、「ふくがいる」の踊ってる家の庭で
「亥の子の晩に重箱ひろてあけてみたら重兵衛はんのきんだま
にぎってみたらほこほこまんじゅう、ひとーつ、祝いましょう」と
いう歌(この歌の文句に似たものは近畿あたりの亥の子の日に多い)を歌って、
ビシビシバシビシ地面をたたくんだソウナ。
なかなか壮大だったのね。げこげこ
フルーツくれます。「うしろすがたのびじょ」さんです。
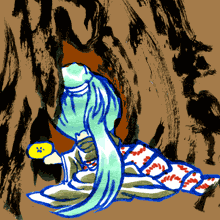
日向の国の木城につたわるもので、
山にあった鍾乳洞のなかにいたふしぎな女。
村人がお膳を借りに行くと貸してくれましたが、
受け渡しをしたり話をしたりするとき
いつも後ろ向きでしゃべるのが特徴だったといいます。
おなじ日向の国の東海に伝わる
「ことづか」(琴塚)のやまんばと大体性格は同じみたいです。
また、柿や蜜柑といった果物をくれ、と頼むと
欲しい数だけくれたりもしましたが、
必要以上の数を考えて言ったりすると
ひとつもくれなかったといいます。
ある時、男が顔をじっくり間近にみてみようと
だきついて引き寄せたところ、穴の奥底に逃げてしまい、
それからはお膳を貸したり果物をくれたりしてくれなくなったトカ。
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
Logo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党