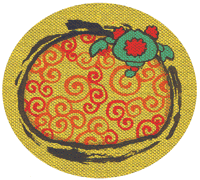氷厘亭氷泉の活動やラクガキをいろいろお届けしているブログです。
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは
おおおおきなカエルの報恩。「きょあ」さんです。

おおおおきなカエルの報恩。「きょあ」さんです。

漢字でかくと「巨蛙」ですあ。
むかし盧伯玉(ろはくぎょく)というひとが登庁しようと歩いてると、
おおきなかえるがものを訴えるような目つきでジーッと見て来たので
「これはふしぎだ」
と思い、しもべにそのあとを追わせます。
すると一ッの古井戸の中にかえるはドブン。
捜索してみると中から死体が見つかりました。
調べてみると、それは行方知れずになってた人で、
お金目当てで殺されてたことがわかり犯人も捕まりました。
そのひとの家族にきいたところ
「あのひとは生前かえるを大事にしてて、
食べるということは決してしなかった人でした」
と言われたソウナ。
『南村輟耕録』などにあるもの。
同じ盧伯玉(盧文璧)でも、巨「蛙」が巨「亀」にかわってる話もあります。
ほんじつの「和漢百魅缶」へのアップは
昨日がたぬきなので、今日はきつね。「きおいちょうのでんしゃ」さんです。
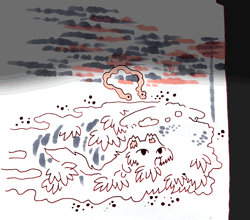
昨日がたぬきなので、今日はきつね。「きおいちょうのでんしゃ」さんです。
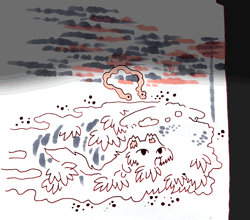
東京の紀尾井町あたりにすんでたきつねで、
赤坂あたりを走る都電の「音」を夜中にガタゴトチンチンと鳴らして
ひとを化かしたりした(行ってみても電車なぞの姿はぜったい見えない)といいます。
明治40年代には既に「古狐」だったそうですから、
明治30年代に電車がとおるようなった前は
馬車の真似とかをしてたのかもしれません。
プロフィール
■雅号
氷厘亭氷泉(こおりんてい ひょーせん)
■ホームページ
■職業
イラストレーター
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
カテゴリー
最新記事
(01/12)
(01/11)
(01/10)
(01/09)
(01/08)
最新コメント
[01/24 دکوراسیون منزل]
[11/29 NONAME]
[05/08 100]
[01/13 佐藤]
[01/05 ひょ―せん]
アーカイブ
新・妖怪党 部署一覧
Logo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
最新トラックバック
フリーエリア