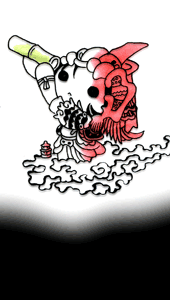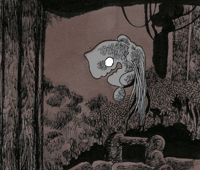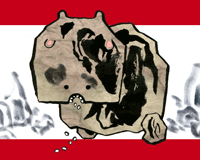徳島県からはいどうぞ。「ほうじょうざかのたぬき」さんです。

阿波の国の三好郡の北条坂という坂道にいたおたぬきさん。
若い女性のすがたに化けてあらわれて
「おんぶしてくれ」
と歩いてるひとに頼んできたといいます。
背負ってると突然「あははははは」と笑い出て
岩石にすり変わってしまったソウナ。
広島県からはいどうぞ。「みなんどぶちのだいじゃ」さんです。
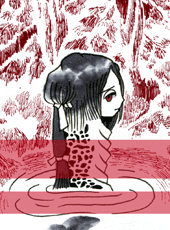
先月のしばり、47都道府県すごろくの岡山県から先がスタートでありますコロン。
安芸の国の湯来につたわるもの。
むかし、みなんどという名前の美しいさむらいがいたのですが、
その妻の正体は実は淵にすむ大蛇で、
あるとき、毎夜毎夜妻がどこかに行くのをつけていったみなんどが
それを知ったことに気づくと、淵に身を投げて大蛇の姿に変じて
二度とみなんどの前に姿を見せることはなかったといいます。
以後毎年、大蛇が沈んだ日になると
淵の中の水が真っ赤に変わったりしたソウナ。
岡山県からはいどうぞ。「ながばかま」さんです。

六口島につたわるもの。
6月23日(由加山のおまつりの日)の夜、
海にたってる千貫岩という岩の上に立ってるという
長袴をはいたさむらいの姿をしてるというおばけ。
(「ながばかまが立つ」って呼んでたそうです)
大きな音がいきなりしたと思うと、岩の上に立ってるそうで、
見たひとは恐ろしくて病気になったりしたといいます。
これで、47都道府県すごろくしばりでおとどけしてまいりました
今月の和漢百魅缶、無事に北海道から岡山県まで踏破いたしました。
来月は、さっそく47都道府県ののこり、
広島県から沖縄県までをひきつづきお送り申し上げます。
大阪府からはいどうぞ。「げんざえもんぎつね」さんです。
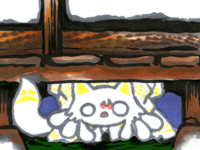
堺の妙慶寺に長年にわたってすんでるというきつね。
源左衛門のなわばりを汚したり、いたずらしたりすると、
怒って取り憑いて来たりもしたといいます。
むかし、きぬ屋という織物商にやとわれてた下女が
このお寺でおしっこをしたところ、
そこにちょうど源左衛門がいた(めにはみえなかった)ため
おしっこひっかけられて怒った源左衛門が
その下女に取り憑いて挙動をおかしくしてしまいます。
これは大変だ、と思った主人たちがお寺に相談したところ
日昌という和尚さんが、源左衛門と相談。(できるとこが便利だね)
「わしに小便をかけたふとどきな下女に詫び状を書かせればゆるす」と
源左衛門からの示談申し出がでたと思ったら
文字なんか一文字も書けないはずの下女が突然サラサラと詫び状をしたため、
次の日にはすっかりモトに戻ったといいます。
京都府からはいどうぞ。「おおへびのあねいもと」さんです。

丹後の国の与謝郡菅野などにつたわるもの。
山の中にすんでる大きなへびの姉妹。
むかし、母親が病気だとの知らせをうけて家にもどる娘が、
山道の途中で女に化けたおおへびの姉に出遭い、
「すまんがこの先にしばらく行ったところにわしの妹がおるで、この手紙を渡してくれんか」
と頼まれます。
娘がまた山道を進むとひとりの坊さんに出遭い、
どうして急いでるのかきかれたので、母親のことと手紙のことを話すと
坊さんは手紙の中身を確認。
すると「この手紙を持って行った人間をやるから喰ってくれ」という内容だったのでびっくり。
手紙の中身を書き換えて娘に渡してあげます。
しばらく行くと、さっきの女に似た女がいたので
娘が手紙を渡すと
「おまえはかわいそうに、親の具合が悪いんか、これで孝行せえ」
といっぱいお金をくれたソウナ。
お手紙を届ける昔話のシリーズざんす。
絵草紙&錦絵研究人
まんが描き
こっとんきゃんでい 主宰
山田の歴史を語る会 同人
新・妖怪党 党しゅ
Logo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党
Logo:Koorintei Hyousen
YoukaitoLogo:Cyusonzi Ryunosuke
Design:O-Onigami Georgenomikoto
2008 新・妖怪党